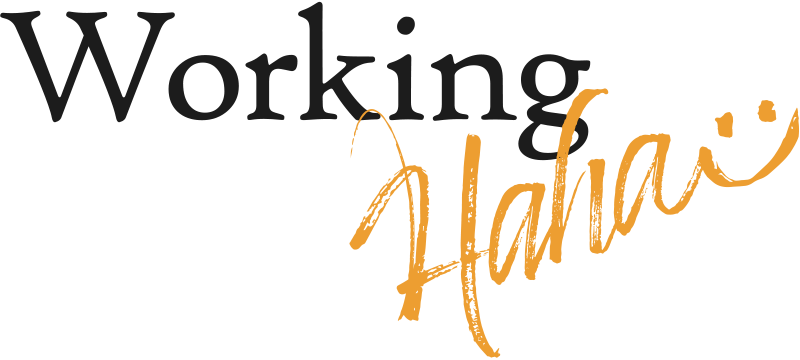こんにちは、Working Haha編集部です!
「読書好きの子どもに育てたいけれど、忙しくてどんな本を選べばいいかわからない」と悩むママ、多いですよね。実は、小学生の時期は心の成長が著しく、本を通して想像力や共感力、思考力がぐんと伸びる大切な時期です。今回は、読書習慣を無理なく取り入れるコツや、小学生におすすめの本をご紹介します!
読書の現状:子どもたちの読書習慣はどうなっているの?

2023年10月に発表された国立国会図書館国際子ども図書館「小学生から高校生の読書に関する7年間の追跡調査」の結果によると、現代の子どもたちの読書時間は減少傾向にあります。
主な調査結果
- 平日の読書時間が0分と答えた子どもは、全体の49%に達しました。
- 読書時間の平均は、2015年の18.2分から2022年には15.2分へと減少。
- 高学年・中学生・高校生になるほど読書時間が短くなる傾向が見られます。
一方で、調査は早期の読書習慣の重要性も明らかにしています。小学校入学前に週4日以上の読み聞かせを受けた子どもは、そうでない子どもと比べて、その後の読書時間が1.5~2倍長くなる傾向があるとのことです。
読書のメリット:データが示す読書の力
同調査では、読書時間が子どもたちの自己評価や能力に大きな影響を与えることが示されています。
読書の効果
- 自己評価が高い
1日1時間以上の読書をする「多読層」の子どもは、理解力・思考力・表現力に対する自己評価が高い傾向があります。 - ニュースへの関心が高まる
読書をしている子どもほど、時事問題や社会の出来事に関心を持つ傾向があります。 - 将来の目標が明確になる
読書時間が長い子どもほど、自分の未来について自信を持ち、目標を設定しやすいとの結果が得られました。
これらのデータからも、読書が単なる娯楽ではなく、子どもの未来を形作る重要な要素であることがわかります。
早期の読書習慣が生み出す未来
さらに同調査では、以下のような興味深い結果が発表されています。
- 早期の読み聞かせが週4日以上行われた子どもは、その後の読書時間が1.5~2倍長くなる傾向がある。
- 読書時間が長い子どもほど、自己評価が高く、ニュースへの関心や将来の目標設定能力が高い。
読書は、単なる趣味ではなく、子どもの心や学び、未来を支える「最高のギフト」なのです。
【出典】国立国会図書館国際子ども図書館「小学生から高校生の読書に関する7年間の追跡調査」
小学生の成長を支える読書の力

なぜ今、小学生の読書が注目されているの?
その背景には、私たち働くママが抱える「子どもの未来への不安」があるのかもしれません。AIやテクノロジーが進化し続ける現代では、子どもたちに求められるスキルも変化しています。その中で、読書が「人間らしさ」を育む重要な活動として再評価されているのです。
実際、先輩ママからはこんな声が寄せられています。
- 「ショート動画やゲームばかりで、想像力が育たないのではと心配。」
- 「学校の授業についていけるか不安。読書を通じて基礎力をつけさせたい。」
そんな共通の悩みを解決する手段の一つとして、読書が注目されているのです。
読書が育む「3つの力」
読書には、子どもの成長に欠かせない大きな力があることをご存知ですか?専門家や教育者にお話を伺ったところ、読書が育む以下の「3つの力」が浮かび上がってきました。
1. 想像力
文字だけで描かれる情景を思い浮かべる力が、子どもの創造性を育みます。
「読書好きな子どもは、難しい問題にも柔軟にアプローチできる」との先生の声もありました。この想像力は、AIには真似できない発想力の基礎となり、未来の可能性を広げてくれるでしょう。
2. 共感力
物語の登場人物の気持ちを理解することで、他者への共感力が育ちます。
「読書を通じて様々な境遇の人の気持ちを知ることで、息子の友達関係が良くなった」という先輩ママの体験談も。共感力は人間関係を築くうえで欠かせないスキルです。
3. 思考力
読書は、論理的思考力や批判的思考力を養う場でもあります。
「本を読んだ後の感想を聞くようにしたら、娘の考える力が明らかに伸びた」という嬉しい報告がありました。読んだ内容を自分の言葉でまとめる過程が、子どもの頭の中を整理し、深い理解へとつながります。いました。忙しい毎日ですが、少しずつでも読書の習慣をつけていく価値は十分にありそうですね。
年齢別・おすすめ本リスト:低学年(1-3年生)向け

冒険と発見の世界へようこそ!
低学年の子どもたちにとって、本は新しい世界への扉です。この時期にピッタリな本を選ぶポイントは、子どもの興味を引き出しながら、物語を楽しむ力を育むこと。WorkingHaha編集部が先生や図書館司書、そして先輩ママたちの意見をもとに厳選した「低学年向けおすすめ本リスト」をご紹介します!
おすすめ本リスト
『かいけつゾロリ』シリーズ
著者:原ゆたか
- ユーモアたっぷりの冒険物語で、主人公ゾロリのひらめきに子どもたちも夢中!
- ママの声:「息子が初めて自分から読みたいと言った本でした。笑いながら読めて大満足!」
➡ 冒険好きな子にぴったり!
『まほうのコップ』
著者:藤田千枝
- 日常に潜む「ふしぎ」を科学で解き明かす絵本。親子で実験を楽しむきっかけにも。
- ママの声:「娘と一緒に実験して、科学の楽しさを共有できました。」
➡ 好奇心旺盛な子どもにおすすめ!
『ぼくは王さま』シリーズ
著者:寺村輝夫
- 王さまのユニークな発想と温かいユーモアにあふれた物語集。短編形式で読みやすいのも魅力です。
- ママの声:「親子で笑いながら読んでいます。想像力が育つのを実感しています!」
➡ 親子で楽しい時間を過ごしたい方に!
『おしり探偵』シリーズ
著者:トロル
- 「フーム、においますね」が決め台詞の、おしり探偵が事件を解決するミステリー。ユーモアと謎解きで人気!
- ママの声:「推理ものに初めてハマった作品。クイズ感覚で楽しめるのが良いですね。」
➡ 謎解き好きや笑いが好きな子にぴったり!
『理科ダマンが教える!キミがヒーローになるための自由研究』
著者:理科ダマン
- 科学好き必見!実験や観察がヒーローの視点で語られるユニークな一冊。自由研究にも活用できます。
- ママの声:「息子が科学に興味を持ち始めたきっかけの本です。」
➡ 理科が好き、または苦手克服を目指す子どもに!
『最強王図鑑』シリーズ
監修:今泉忠明
- 恐竜、昆虫、動物など、さまざまなジャンルで「最強」を競わせる図鑑。見て読むだけで楽しく学べます。
- ママの声:「動物好きの子どもにドンピシャ!知識が自然と増えます。」
➡ 生き物が好きで、ワクワクを求める子どもに!
さらにおすすめ!
『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』(廣嶋玲子著)
子どもたちの願い事をかなえる不思議なお菓子が登場する物語。「続きが気になって一気読み!」との声多数。
『おばけのバーバパパ』シリーズ(アネット・チゾン、タラス・テイラー著)
カラフルでかわいいバーバパパ一家が繰り広げるドタバタ劇。「絵を見ているだけでも楽しい」と好評!
低学年(1-3年生)向け本選びのコツ
- 興味を優先して本を選ぼう
おしり探偵や最強王図鑑のような人気シリーズは、本嫌いな子でも手に取りやすいです。 - 読み聞かせで読書の入り口をつくる
低学年でも読み聞かせは有効!寝る前に親が読んであげると、本への興味が広がります。 - 図書館や書店を積極活用
図書館で色々な本を見せて選ばせると、自分の好みが見えてきますよ。
年齢別・おすすめ本リスト:高学年(4-6年生)向け

深い思考と感動の物語へようこそ
高学年になると、物語の奥深さやキャラクターの心情を理解し、より複雑なテーマに触れられるようになります。一方で、スマホやゲームに惹かれる時期でもあり、読書の時間をつくるのが難しいと感じるママも多いのでは?そんな時こそ、子どもが夢中になれる本を選ぶことがポイントです。専門家や先輩ママたちのおすすめをもとに、高学年向けの本を厳選しました!
おすすめ本リスト
『西の魔女が死んだ』
著者:梨木香歩
- 思春期特有の悩みと、おばあちゃんとの絆を描いた心温まる物語。主人公が成長していく姿に、多くの子どもが共感するでしょう。
- ママの声:「娘と一緒に読んで、人生について話し合うきっかけになりました。」
➡ 自分や家族について深く考えられる本を探している子におすすめ!
『科学がみるみるわかる奇想天外実験図鑑』
監修:尾嶋好美
- 身近な材料を使って科学の面白さを体験できる実験図鑑。自由研究にもピッタリ!
- ママの声:「息子が自由研究のアイデアを自分で探せるようになり、科学への興味が深まりました。」
➡ 理科好きや好奇心旺盛な子どもにピッタリ!
『霧のむこうのふしぎな町』
著者:柏葉幸子
- ファンタジーと現実が交錯する不思議な物語。主人公リナの成長や異世界の描写に、読者は引き込まれます。
- ママの声:「読んでから作文の内容が格段に良くなり、想像力が豊かになったと感じます。」
➡ 想像力を育み、物語の世界に浸りたい子どもに最適!
さらにおすすめ!
『ざんねんな生き物事典』(今泉忠明監修)
動物のユニークな特徴や行動を楽しく学べる一冊。「学校で友だちと話題にして盛り上がっている」という声も!わせて本を選ぶのがコツ」というアドバイスがありました。図書館の司書さんに相談するのも良いかもしれません。
『ぼくらの七日間戦争』(宗田理著)
社会問題や友情を描いた名作。アクションとスリルが詰まっていて、読書が苦手な子もハマりやすい!
『Wonder ワンダー』(R.J.パラシオ著)
生まれつき顔に障がいを持つ男の子の物語。困難を乗り越え、周囲と向き合う姿に感動すること間違いなし。
高学年(4-6年生)向け本選びのコツ
- 子どもの個性に寄り添った本選びを
この年代になると個性がはっきりしてきます。好きなジャンルやテーマに合わせて選んであげると、自分から本を読むようになります。 - 親子で読書感想を話し合おう
子どもの読んだ本について聞くと、驚くほど深い感想が出てくることも!親子のコミュニケーションのきっかけにもなりますよ。 - 図書館や司書さんを活用する
図書館の司書さんに相談すると、子どもの興味や読解力に合った本を教えてくれます。親も新しい発見があるかもしれません!
忙しい毎日でもできる!読書習慣の始め方

読書は子どもの心を育む大切な習慣ですが、忙しい毎日の中で時間を確保するのは簡単ではありません。そこで、手軽に始められる3つのアイデアをご紹介します。無理なく読書を生活に取り入れ、親子で楽しむ時間を作ってみましょう!
1. 図書館を活用する
図書館は「本との出会いの場」として最適です。親子で図書館に行き、一緒に本を選ぶ時間を楽しむことで、子どもの読書意欲が高まります。
- おすすめの工夫
- 「今日は3冊選んでみよう」と声をかけ、選ぶ楽しさを共有。
- 子どもが興味を持ちそうな本を親も一緒に手に取ることで、読書へのハードルを下げられます。
- 定期的に図書館の日を設けて「本を選ぶ習慣」を作る。
ママの声
「図書館に行くと、自分では選ばないジャンルの本に興味を持つことも。子どもの意外な一面が見られて楽しいです!子どもの読みたい気持ちを優先し、どんな本でも口出しせずに自由に選ばせています。」
2. 短時間から始める
忙しい日々でも、短い時間から読書習慣を取り入れてみましょう。家族全員がリビングで本を読む時間を設けると、自然と読書が生活に溶け込みます。
- スタートのヒント
- 最初は1日10分から。タイマーをセットして読書タイムを楽しみましょう。
- 子どもが読む本と同じテーマの本を親が読むのもおすすめ。読後の会話が盛り上がります!
- テレビやスマホを一時的にオフにして、家族で「静かな時間」を共有。
ママの声
「10分から始めた読書タイムが、いつの間にか30分に。子どもが好きなシリーズものに出会い、時間があっという間に過ぎていくようです。家族で感想を話し合う時間も楽しいですよ!」
3. 電子書籍を取り入れる
外出先や移動中にも読書が楽しめる電子書籍は、忙しいママにもピッタリです。
- 取り入れ方のポイント
- 子ども向けの電子書籍サービスを利用して、お気に入りの一冊を見つけましょう。
- 通勤中や子どもの習い事の待ち時間に、親も電子書籍で読書を楽しむ姿を見せると、子どもの刺激になります。
- 電子書籍リーダーを家族で共有することで、使いやすさがアップ!
ママの声
「タブレットを使うと、紙の本には見向きしなかった息子も『これ読んでみようかな』と興味を持つようになりました。特に、移動中や待ち時間での時間つぶしに最適!私自身も気軽に読書が楽しめて、一石二鳥です。」
よくある質問 Q&A
WorkingHaha編集部に寄せられた、読者からのよくある質問にお答えします。
Q1: 子どもが本を読みたがらないのですが、どうすれば興味を持ってもらえますか?
A: 子どもの読書への興味を引き出すのは、少し工夫が必要ですが、焦らずに進めることがポイントです。先輩ママや専門家の意見をもとに、以下のアイデアを試してみてください。
1. 好きなアニメや映画の原作本を探してみる
子どもの好きなキャラクターや物語に関連する本を手に取ることで、親しみやすさが増します。例えば、アニメ「おしり探偵」が好きなら、同シリーズの本をおすすめします。
2. 図書館で自分自身に本を選ばせる
図書館は本を選ぶ楽しさを教えてくれる絶好の場所。親が選ぶのではなく、子ども自身が「これを読んでみたい!」と思える本を見つける場にしましょう。
3. 親子で同じ本を読んで感想を話し合う
「親子読書クラブ」として、同じ本を読んで感想を話し合う時間を作ってみてください。子どもが本を読む意欲を高めるだけでなく、親子の会話も広がります。
ママの体験談
「息子が昆虫好きだったので、まずは『最強王図鑑』や昆虫図鑑を読ませました。徐々に虫が主人公の冒険物語や科学系の本に興味を持ち始め、気づけば自分で本を選ぶように!無理せず好きなことから始めるのがコツだと実感しました。」
Q2: 読書感想文の宿題で困っています。上手な書き方のコツはありますか?
A: 読書感想文は、多くのママたちが悩むポイントですよね。でも、ちょっとした工夫で子どもがスムーズに書けるようになる方法があります。教育専門家や先輩ママのアドバイスをもとに、いくつかのコツをご紹介します。
1. 読み終わったら、すぐにメモを取る
感想文を書くときに一番大事なのは、新鮮な気持ちを記録すること。子どもに「心に残ったシーン」や「登場人物の気持ち」について、短い言葉でメモを取らせましょう。これが後で感想文を書くときのヒントになります。
2. 構成を「はじめ・なか・おわり」で考える
感想文を3つのパートに分けると、書きやすくなります。
- はじめ:読んだきっかけや本の簡単な紹介。
- なか:心に残ったシーンや感じたことを具体的に。
- おわり:本を読んで学んだことや、自分の生活への影響。
3. 「なぜそう思ったのか」を具体的に書く
「面白かった」「感動した」だけではなく、「なぜそう思ったのか」を考えるよう促しましょう。
例えば・・・
- 「主人公が勇気を出して行動したところがかっこいいと思った。自分だったら同じことができないから。」
- 「この本を読んで、友達との関係を大切にしようと思った。」
先輩ママの体験談
「感想文を書く前に、家族で本の内容について話し合う時間を作りました。『どのシーンが良かった?』『自分だったらどうする?』と問いかけると、子どもの考えが整理されて感想文がスラスラ書けるように!」
感想文を書く際には、以下のポイントも活用してみてください。
・短い感想から始める
いきなり長文を書くのは難しいので、まずは短い一言からスタートしましょう。
・付箋を活用
読書中に気になったところに付箋を貼ると、後で見返しやすくなります。
Q3: 読書は大切だとわかっていても、勉強や習い事との両立が難しいです。どうバランスを取ればいいでしょうか?
A: 勉強、習い事、読書のバランスを取るのは、忙しい日々を送る働くママにとって確かに大きな課題です。でも、無理なく取り組むコツを知れば、どれも大切にできます。専門家や先輩ママたちのアドバイスを参考に、以下のアイデアを試してみてください。
1. 読書を「息抜き」や「ご褒美」として位置づける
読書を、ストレスの多い日常の中でリフレッシュできる時間として考えると、自然に取り入れやすくなります。
- 例:勉強や習い事を頑張った後に、「好きな本を10分読む」時間をプレゼントしてみましょう。
ママの声:「読書を勉強のご褒美にしたら、息子が喜んで読書時間を楽しむようになりました!」
2. 勉強の合間に短い読書タイムを入れる
長時間の勉強は集中力が続きません。読書を「頭の切り替え」に使うことで、学習効果が上がることも。
- 例:「30分勉強したら10分読書」と、タイマーを使って時間を区切る方法が効果的です。
3. 教科に関連した本を選んで「学び」を補完する
学校で習う内容や子どもの興味を引き出すテーマの本を選ぶと、勉強との相乗効果が期待できます。
- 例:
- 理科が好きな子には『理科ダマン』や『最強王図鑑』
- 社会に興味があれば『ざんねんな歴史人物』や伝記シリーズ
専門家の意見:「読書を学習の一部として考えると良いです。語彙力や読解力が育つことで、国語や他の教科の理解度がアップします。長期的には、読書時間が学習全体の効率を上げることにつながります。」
4. 移動時間や待ち時間を活用する
習い事の送迎中や、スキマ時間に電子書籍やオーディオブックを活用するのもおすすめです。
- 電子書籍:お気に入りの本をスマホやタブレットに入れておけば、外出先でも手軽に読書ができます。
- オーディオブック:忙しい時でも「聴く読書」で物語や知識を楽しむことが可能です。
先輩ママの体験談
「娘がピアノの練習や塾で忙しいとき、送迎中の待ち時間を読書タイムにしました。家では疲れて読む時間が取れない分、スキマ時間をうまく使えるようになりました。」
忙しい毎日を送りながらも、子どもの成長を支える読書習慣を取り入れることは、働くママにとって大きなチャレンジかもしれません。それでも、ほんの少しの工夫で、読書の時間は親子の大切なひとときに変わります。
子どもが本を通じて得られる力は、未来への大きな財産です。想像力、共感力、思考力、そして勉強や生活の土台となる語彙力や読解力――これらを育む読書は、短い時間でも積み重ねることで確かな成果をもたらします。
親子で同じ本を楽しむ時間、図書館で本を選ぶワクワクする時間、短いスキマ時間を活かして読む時間。どの形でもかまいません。まずは「読書って楽しい!」と思える瞬間を、子どもと一緒に作ってみませんか?
Working Hahaは、頑張る働くママと子どもの未来を、読書を通じて応援します!