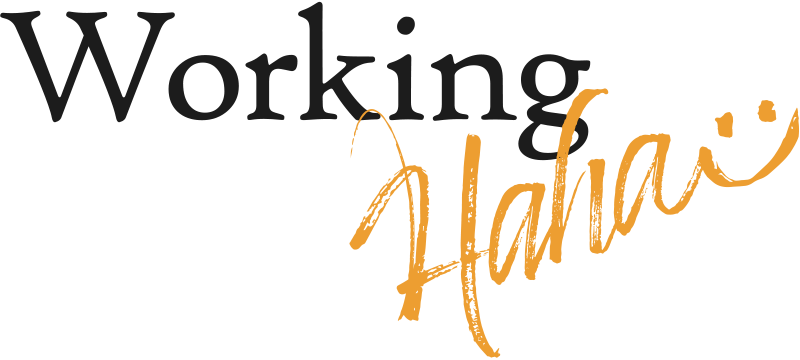こんにちは、WorkingHaha編集部です。小学生のお子さんがいるワーキングマザーのみなさん、学童保育の選択に悩んでいませんか?「学校の学童がいいの?それとも民間の学童?」「どっちがワーママの味方?」そんな声をよく耳にします。
今回は、学校学童と民間学童の違いを徹底比較!それぞれのメリット・デメリットを整理して、あなたの家庭にぴったりの選択ができるようサポートします。さらに、学童を利用しながら仕事と育児を上手に両立するコツもお伝えしちゃいます。
公立学童vs民間学童:基本の違い

近年、学童保育の形態が多様化しており、公立民営の学童も増えてきています。
厚生労働省が公表した「令和 5年 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の実施状況」によれば、学童クラブの運営形態や提供するサービスの幅が広がりを見せています。
詳しい資料は次のリンクからご確認いただけます:厚生労働省 令和 5年 放課後児童健全育成事業(PDF)
以下は、公立学童と民間学童の基本的な違いを整理した表です。
| 項目 | 公立学童 | 民間学童 |
|---|---|---|
| 運営主体 | 自治体や社会福祉協議会が運営 | 民間企業やNPO法人が運営 |
| 場所 | 学校敷地内や近隣施設 | 専用施設、賃貸物件など |
| 費用 | 比較的安価 | やや高額 |
| 利用時間 | 下校時~19時頃(延長あり) | 下校時~19時以降(施設による) |
| プログラム | 基本的な生活ケアが中心 | 学習や体験プログラムが充実 |
公立民営学童とは?
公立民営学童は、自治体が設置した施設を民間企業や団体が運営する形態の学童です。このタイプは、自治体が監修する基本的なサービスをベースに、民間運営ならではの柔軟なプログラムや延長保育を提供するケースが多いです。これにより、費用面とプログラムの充実度のバランスが取れていることが特徴です。
先輩ママはどうやって選んだ?
公立学童を選んだママの声
ママの体験談(30代・子ども1人)
「うちの子は公立学童に通っています。同じ学校の友達と一緒に過ごせるので安心感があります。私の職場からも近く、送り迎えがしやすいのも大きなポイントでした。一度見学に行き、先生たちの雰囲気や子どもたちの様子を確認してから申し込みました。」
ママの体験談(40代・子ども2人)
「費用が手頃なので学校併設の公立学童を選びました。指導員の方々がしっかりサポートしてくれるので、放課後も安心して預けられます。ただ、利用時間が限られているので、仕事の調整が必要になることもあります。」
民間学童を選んだママの声
ママの体験談(30代・子ども1人)
「民間学童に通わせています。夜遅くまで対応してくれるので、仕事が長引いても安心です。英語やアートのプログラムが充実しており、子どもも楽しんで通っています。」
ママの体験談(40代・子ども2人)
「子どもの性格に合った少人数制の環境を重視して、民間学童を選びました。最初は費用が心配でしたが、車での送り迎えのサービスや充実した内容を考えると納得のコストだと思います。」
公立学童のメリット・デメリット
メリット
- 費用が安く経済的
- 学校の友達と一緒に過ごせる
- 環境の変化が少なく子供が安心
- 学校の先生との連携が取りやすい
デメリット
- 利用時間が限られる(特に長期休暇中)
- プログラムの種類が少ない
- 学年が上がると利用できない場合も
ママの体験談
「人見知りなうちの子には、学校併設の学童が最適でした。同じクラスの友達と一緒なので安心して通えています。放課後に校庭で思いっきり遊べるのも楽しいようです。」
民間学童のメリット・デメリット
メリット
- 夜遅くまで、休日も対応可能
- 多彩な学習・体験プログラム
- 少人数制で手厚いサポート
- 送迎サービスがある場合も
デメリット
- 費用が高い
- 学校の友達と離れることがある
- 移動時の安全面に注意が必要
ママの体験談
「少しコストが高いので悩みましたが、民間学童に通わせて良かったです。英語やスポーツのプログラムが充実していて、習い事代わりにもなっています。」
ワーママの働き方別おすすめ学童

あなたの働き方に合わせて、最適な学童選びをご提案します。
定時で帰れる → 公立学童
- 18時頃までのお迎えが可能なら、費用も抑えられて安心です。
- 子供が学校の友達と一緒に過ごせるため、環境の変化が少なく安心感があります。
残業が多い→ 民間学童
- 夜遅くまで対応してくれる学童なら、残業が発生しても安心。
- 英語やプログラミングなどのプログラムが充実している場合もあり、子供の学びの場としても魅力的です。
フレックスタイム制 → 公立学童+民間学童
- 基本的には公立学童を利用し、急な残業や不規則なスケジュールが発生した場合は民間学童を一時利用する「ハイブリッド型」が便利です。
- 柔軟な対応が可能で、コスト面でも効率的です。
在宅ワーク → 公立学童
- 自宅近くの公立学童を利用すれば、仕事の合間に子供の様子を確認しやすいです。
- 学童からの連絡があった場合にも対応がスムーズ。
シフト制 → 民間学童
- 土日や長時間保育に対応している学童も多いので、仕事の調整がしやすくなります。
- 不規則な勤務時間や休日出勤にも対応してくれる民間学童は、シフト制のママにとって心強い選択肢です。
編集部ママの工夫
「私は基本的に在宅ワークですが、月に数回の出社が必要です。そんな時だけ民間学童の一時利用をしています。柔軟な対応をしてくれるので、本当に助かっています!」
学童選びの5つのポイント

1. 子供の性格と相性
お子さんが集団活動が得意で、同じ学校の友達と一緒に過ごしたい場合は、公立学童が適しています。一方、集団行動が苦手だったり、少人数で落ち着いて過ごしたい子には民間学童がおすすめです。特に、民間学童では個別対応が充実している場合が多く、指導員が子供一人ひとりの個性に寄り添うことが可能です。
2. 家庭の価値観
ご家庭で大切にしていることが学童選びにも影響します。学習面を重視し、子供に新しいスキルを身につけてほしいと考えるなら、プログラムが豊富な民間学童が最適です。一方で、放課後はリラックスして友達と遊ぶ時間を大切にしたい場合は、公立学童が良い選択となるでしょう。
3. 仕事のスケジュール
定時で帰れる仕事なら公立学童でも対応可能ですが、不規則な勤務や残業が多い場合は柔軟な民間学童が便利です。民間学童の中には夜遅くまで対応してくれる施設や、シフト制に合わせた利用プランを提供しているところもあります。あなたの働き方に合った選択がポイントです。
4. 費用対効果
学童にかかる費用はご家庭にとって大きなポイントです。公立学童は費用が抑えられる反面、プログラムやサービスに制限があることがあります。民間学童は費用が高めですが、英語やプログラミングなど充実した内容が含まれている場合も多く、長期的なメリットを考えることが重要です。
5. 立地と送迎の利便性
学童の場所が自宅や職場から通いやすいかどうかも重要です。特に送り迎えの時間が限られているワーママにとっては、学童が通勤ルート上にあるか、自宅の近くにあるかで選びやすさが変わります。また、民間学童には送迎サービスを提供している施設もあるため、そういったオプションを活用するのもおすすめです。
編集部のアドバイス
選択肢がある場合は、必ず見学や体験利用をしてみることをおすすめします。お子さん自身がその場所で楽しく過ごせるかどうかを確認することが最も重要です。
仕事と育児を両立させるコツ

学童を上手に活用しながら、仕事と育児を両立させるための具体的なヒントをご紹介します。
1. 職場との綿密なコミュニケーション
- 学童のお迎え時間を考慮したスケジュールを上司や同僚に相談し、理解を得ることが重要です。
- 勤務時間の調整や在宅勤務の導入が可能であれば、積極的に活用しましょう。
2. 緊急時のバックアッププラン
- 子供の急な発熱や学校からの連絡に備え、あらかじめお迎えを代行できる家族や友人を確保しておくと安心です。
- 民間サービスの「緊急一時預かり」なども調べておくと、さらに対応力が高まります。
3. 子供との質の高い時間作り
- 学童のお迎え後は、スマホや仕事を一旦脇に置き、子供と向き合う時間を確保します。
- 一緒に宿題を見たり、その日あった出来事を聞くことで、子供との信頼関係が深まります。
4. 家事の効率化
- 平日の家事負担を減らすため、週末に食材をまとめて準備する「作り置き」や、家事代行サービスの活用を検討しましょう。
- 子供にも簡単な家事を手伝ってもらい、家庭の負担を分散させることもおすすめです。
5. 自分時間の確保
- 子供が学童にいる間に美容院やカフェでの息抜き時間を確保し、自分のリフレッシュを忘れないようにします。
- 自分を労わることで、家庭や仕事にも前向きに取り組むエネルギーが生まれます。
編集部ママの体験談
「毎週金曜日は『ごほうびデー』にしています。学童のお迎え後、子供と一緒に外食をすることに。家事をしなくていい分、子どもとじっくり向き合って話をすることができるんです。私にとっても子どもにとってもいいリフレッシュになっています。」
まとめ:ぴったりの学童を見つけよう
学童選びは、家庭の状況や働き方、お子さんの性格などさまざまな要素を考慮する必要があります。完璧な選択はないかもしれませんが、見学や体験利用を通じて、お子さんが楽しく過ごせる環境を見つけることが大切です。
また、学童を賢く活用することで、仕事と育児の両立がぐっと楽になります。お子さんの成長を支える素晴らしい学童生活が、あなたの家庭に幸せをもたらしますように。
WorkingHahaは、頑張るワーママをいつでも応援しています!